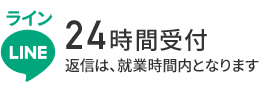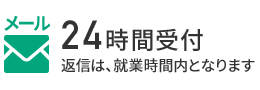遺言書作成
遺産相続手続
サポートサービス
遺言書作成
遺言書とは
遺言は、自分の財産を誰に、どのように相続させたいかを書き記したもの
以前は、「自分の財産を分ける」ために作成されるというイメージがありましたが、現在では、以下のように作成される方が増えています。
○ 相続人や家族に余計な面倒をかけないため
○ ご自分の想いを伝えるため
確かに、遺言は法律上、作成する義務があるわけではありません。しかし、遺言書がないケースでは法定相続人による遺産分割協議が必要になり、その協議をまとめるのも大変な作業になります。また、相続人が多数いる場合は無用な争いの火種になりかねません。


遺言書は家族への最後のメッセージ
遺言には、付言事項として
○ ご自分の葬儀の方法
○ 家族への感謝の気持ち
○ 遺言を残した経緯
○ 分割方法の理由
を書くことができます。
遺言を活用して、ご自分の財産の行先を決め、家族への想いを残すことは決して後ろ向きなことではありません。
遺言書原案の作成、内容の精査、戸籍謄本等の収集、相続関係図などの作成、証人就任など、公正証書遺言作成に必要な手続きのお手伝いをいたします。遺言の内容を実現する為に遺言執行者に就任いたします。
また、必要性があれば、高齢者の方やそのご家族の方に代わって財産管理及び身上監護を行います。そして判断能力の衰えた場合に備えて任意後見契約を結び、安心して生活していただけるようにサポートさせていただきます。
公正証書遺言の
作成方法
公正証書遺言の作成の主な流れです。行政書士が事前に打ち合わせをしていますので、ご本人は、当日公証人が遺言の内容を読み上げながら確認します。そして、証書に記名押印をするという流れになります。
-

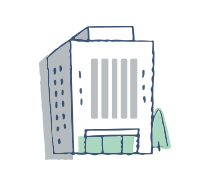
証人2人以上の立会いのもと公証人役場へ出向く(別途依頼により公証人の出張もあります)
-
-


遺言者が遺言の内容を公証人に口述する
-
-


公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させる
-
-

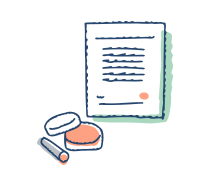
遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名・捺印する
-
-

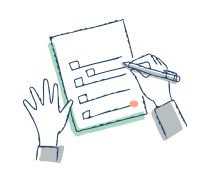
公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印する
公正証書遺言の
必要書類
公正証書遺言の必要書類は以下のとおりです。 戸籍等の公的書類は、行政書士が相続関係説明図作成を前提として職務上請求して取得することができます。
- 遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)とその実印
- 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
- 相続人以外の方に遺贈する場合はその方の住民票
- 相続又は遺贈させる財産が不動産の場合は、登記簿謄本と固定資産納税通知書
- 動産の場合はそれらを記載したメモ
- 預貯金の場合は金融機関名、支店名、口座番号
- 証人2名の住所、氏名、職業、生年月日
報酬・費用
| 業務 | 報酬 | 手数料・印紙代 |
|---|---|---|
| 公正証書遺言書作成 | 100,000円~ | 実費 |
✳︎ 報酬額は事案によって異なりますので、お話をお伺いしてお見積もりをさせていただきます。
遺産相続手続
相続について
「相続」はすぐに進まない?
実際にかかる手間と時間
相続が発生すると、心理的に落ち着くまで時間がかかりますし、相続人が多くいる場合は遺産分割協議に大変な手間と時間を要します。また、誰が法定相続人なのかを戸籍謄本や改製原戸籍、除籍を取寄せて相続人を確定させなければなりませんし、地元ではない場合は郵便で戸籍等を請求しなければならない場合があります。
また、普段から付き合いのある間柄どうしが相続人であれば話し合いもしやすいですが、 一度も顔をあわせたことのない方が相続人であった場合には、連絡がとれなくて、遺産分割協議にすら入れないというケースもあるのです。


相続手続きの不安を解消するワンストップサービス
令和6年4月1日から、相続や遺贈により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請(登記申請の代理は司法書士業務になります。)をしなければならなくなりました。正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料が科されることがありえます。ご依頼者からお話をお伺いした後は、役所から戸籍謄本、改製原戸籍、除籍を取得して相続関係説明図を作成いたします。また、委任状を頂戴し、金融機関などで預貯金などの相続財産を調査いたします。そして、相続人全員で遺産分割協議をまとめていただき、遺産分割協議書を作成いたします。
また、遺産分割協議書作成後の金融機関における預貯金、有価証券の解約、名義変更、送金手続き、不動産の名義変更(所有権移転登記は提携専門家が行います)、自動車の移転登録手続きも代行いたします。
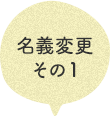
不動産の
名義変更
相続を原因とする土地や建物などの名義変更のお手伝いをします。(登記申請は提携司法書士又はご本人が行います) 相続に関して、以下の書類が必要となります。
【主な必要書類
(法定相続の場合)】
- 被相続人の住民票(除票)
- 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本、改製原戸籍、除籍
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 相続人の住民票
- 遺産分割協議書
- 法定相続人全員の印鑑証明書
- 固定資産の評価が分かる書類
- 相続関係説明図
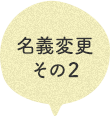
預貯金の
名義変更(解約)
預貯金の名義人が亡くなると、原則その口座は凍結されますので、 相続人名義への変更か解約手続きを、金融機関の窓口で行う必要があります。 これは何度も金融機関の窓口に足を運ばなければならないほか、戸籍謄本も被相続人の出生から 亡くなった時までの連続した戸籍謄本が必要で、この収集も大変な作業となります。 是非、労力とお時間の節約のためにも当事務所のサービスをご利用ください。
【主な必要書類】
- 相続手続依頼書
- 法定相続人全員の印鑑証明書(原本 原則3ヶ月以内)
- 戸籍謄本、改製原戸籍、除籍(原本 原則3ヶ月以内)
- 被相続人の預金通帳、証書
- 相続人代表者の連絡票
- 遺産分割協議書(原本提示)
- 遺言書(原本提示)
- 遺言執行者の印鑑証明書(原本 原則3ヶ月以内)
また、該当があれば、以下の三点が加えて必要となります。
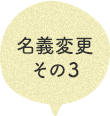
自動車の
名義変更
相続を原因とする自動車の移転登録手続きを代行いたします。 相続に関して、以下の書類が必要となります。
【主な必要書類
(法定相続の場合)】
- 被相続人の戸籍謄本(死亡の事実がわかり、相続人全員の記載のあるもの)
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印で押印)
- 新所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
- 新所有者の委任状
- 車検証(原本)
- 車庫証明(新所有者の住民票上の住所と、車検証上の住所が異なる場合)
報酬・費用
| 業務 | 報酬 | 費用 |
|---|---|---|
| 相続手続一式 | 200,000円~ | 戸籍代、郵便切手代等の実費 |
✳︎ 報酬額は事案によって異なりますので、お話をお伺いしてお見積もりをさせていただきます。